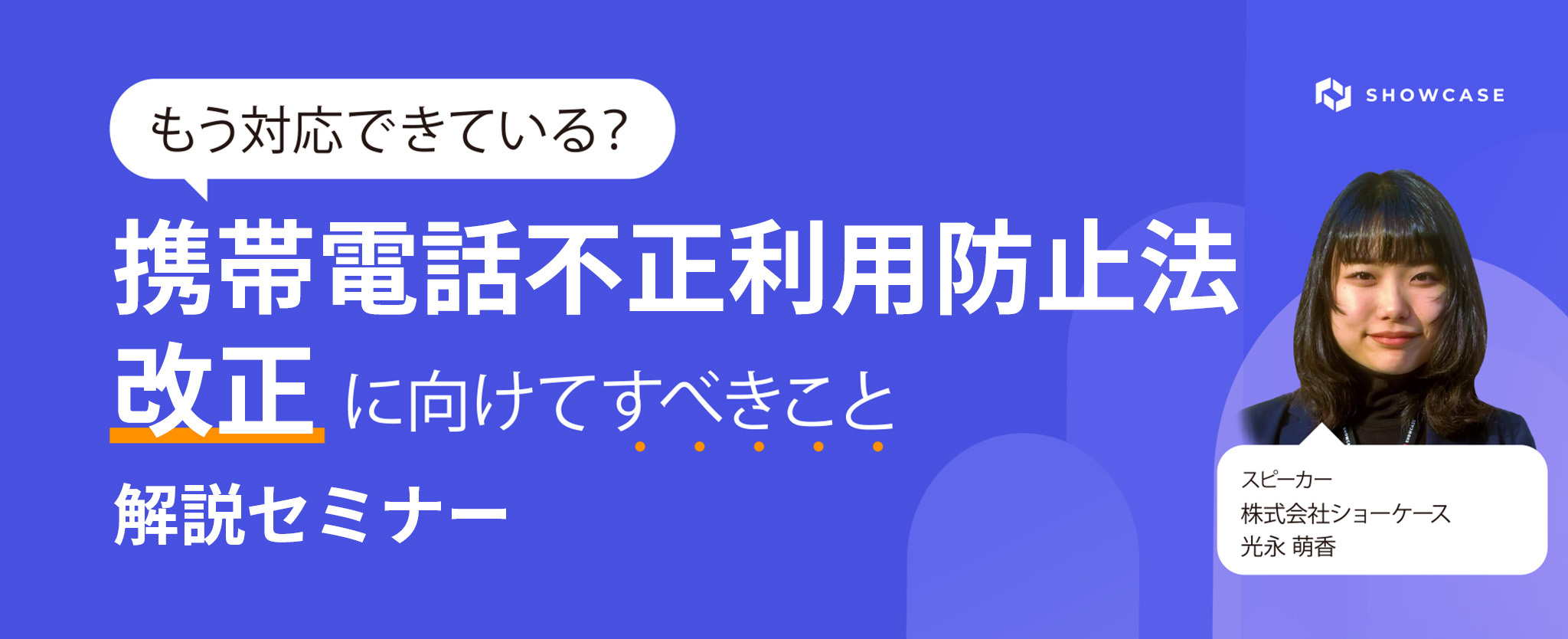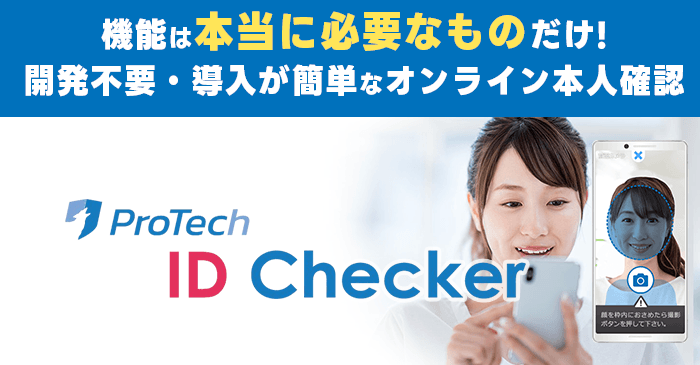2026年4月改正予定|携帯電話不正利用防止法とは?本人確認への影響と対応

携帯電話契約時等の本人確認方法のうち、本人確認書類の写しを用いる方法を廃止する為に携帯電話不正利用防止法の改正が2026年4月に施行される方針が示されました。
この記事では2026年4月施行予定の改正内容や基本的な携帯電話不正利用防止法の内容について解説していきます。
「携帯電話不正利用防止法とはどんな内容なのか」「自社が携帯電話不正利用防止法の対象なのか」「対象になっている場合どのような対応が必要なのか分からない」という人向けて、分かりやすく解説いたします。
携帯電話不正利用防止法とは?
携帯電話不正利用防止法とは、匿名で契約された携帯電話がオレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺等の犯罪に利用されていたことを受けて成立した、携帯電話事業者に契約者の本人確認を契約者の本人確認を身分証明書等に基づいて行うことを義務付けた法律です。(2006年4月施行)
その後、匿名で契約されたレンタル携帯電話の犯罪利用も問題になったことから、携帯電話を業として有償で貸与するレンタル携帯電話業者にも本人確認を義務付ける、携帯電話不正利用防止法の改正が行われました。(2008年12月施行)
2026年4月施行予定の携帯電話不正利用防止法の改正内容とは?
2026年4月1日に施行が予定されている「携帯電話不正利用防止法施行規則」の改正内容が、2025年4月1日に公布されました。
近年、携帯電話を用いた特殊詐欺の被害が深刻化しています。その中でも特に多いのが、精巧に偽変造された本人確認書類を用いて不正に契約された携帯電話が犯行に悪用されるケースです。
このような状況に対応するため、携帯電話等の契約を非対面で行う際の本人確認手続きが、一層厳格化されることになりました。
オンライン上で完結する非対面時の本人確認方法に関連する改正の主なポイントは3点となります。
- ■ 顔写真のある本人確認書類を撮影した画像情報の送信を受ける本人確認方法を廃止する。
- ■ 本人確認書類の写しの送付を受ける本人確認方法を廃止する。
- ■ 顔写真のない本人確認書類を用いる非対面の本人確認方法については、原則廃止するが、偽造・改ざん対策が施された本人確認書類(住民票の写し等)の原本の送付を受ける本人確認方法については、引き続き、一定条件の下、本人確認に利用可能とする。
携帯電話不正利用防止法の規制対象
携帯電話不正利用防止法の規制対象となる事業者は以下です。
| MNO(Mobile Network Operator)移動体通信事業者 | 自社で保有する回線を使って通信サービスを提供する事業者で、MNOと同じ意味で「通信キャリア」というワードもよく用いられています。 |
|---|---|
| MVNO(Mobile Virtual Network Operator)仮想移動体通信事業者 | 自社では回線を保有せず、MNOの事業者の回線を借り受けて通信サービスを提供する事業者です。 |
| 通信端末の販売代理業店 | 「携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者」のことを指します。 |
| レンタル携帯電話事業者 | 「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」をいい、携帯電話やSIMカードなどの「通話可能端末設備等」を、空港等において旅行者向けにレンタルするサービス等がこれに該当します。 |
| IP電話提供事業者 | 2024年4月から、特定IP電話番号(050)を使用した通話を可能とするアプリケーション・ソフトウェアを提供し、スマホやタブレット端末等で通話することを可能とするものを提供する事業者を指します。 いわゆるインターネット回線を使用して通話することができるサービスの提供事業者のことです。 |
携帯電話不正利用防止法に準拠した本人確認
携帯電話不正利用防止法に準拠した上で、安全かつスピーディな本人確認を行う方法としてeKYCサービスがおすすめです。
手間と時間がかかる対面や郵送対応を伴う本人確認方法ではなく、オンラインの非対面本人確認を行うことで、安全でありながらスピーディな本人確認を行うことができます。
ユーザー側としては、対面や郵送対応などの手間がかからないというメリットがあります。
事業主側としては、対面や郵送対応に伴う本人確認作業の工数・コストを削減することができ、ユーザーの申込時の途中離脱を防止することができる等のメリットがあります。
株式会社ショーケースが提供する、オンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」では、携帯電話不正利用防止法にも準拠した本人確認を行うことができます。公的個人認証サービス(JPKI)にも対応しています。
本人確認(KYC)とは
携帯電話事業者が、契約する相手の本人特定事項を公的機関の発行した本人確認書類により確認することを指します。
本人特定事項は、契約者が個人か法人かによって異なります。
個人の本人特定事項
- 氏名
- 住居
- 生年月日
法人の本人特定事項
- 名称
- 本店等の(主たる事務所でもよい)所在地
- 代表者や契約担当者の本人特定事項(氏名+住居+生年月日)
本人確認の方法とは
本人確認の方法は店頭等対面で行われる場合、オンラインでの非対面で行われる場合、契約者が個人である場合、法人である場合によってそれぞれ方法が異なります。
一つずつ解説していきます。
契約者が個人の場合
対面での契約
・対面で提示することで本人確認を完了できる本人確認書類の原本の提示
・提示や送付を受けることに加えて、携帯電話端末などの送付が必要な証明書の原本の提示
+携帯電話端末や契約関係書類を、転送不要郵便物物で送付
※送付する代わりに販売員が住居に訪問し直接交付することも可能
非対面での契約
・ソフトウェア等を通じて契約者本人の顔画像の送信+写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート)に付属するICチップに記録された本人特定事項の送信
・ソフトウェア等を通じて契約者本人の顔画像の送信
+写真付き本人確認書類(本人特定事項の記載や書類の厚み等の特徴も含む)の送信
・対面で提示することで本人確認を完了できる本人確認書類の写し又は提示や送付を受けることに加えて、携帯電話端末などの送付が必要な証明書の原本もしくは写しの送付+携帯電話端末や契約関係書類を転送不要郵便物等で送付
※送付する代わりに販売員が住居に訪問し直接交付することも可能
・特定事項伝達型本人限定受取郵便物等により懈怠電話端末や契約関係書類を送付
※2020年10月1日~利用できる本人確認書類が写真付きのもの限定となる
・電子署名及び電子証明書を付した本人特定事項の送信
契約者が法人の場合
対面での契約
・登記事項証明書等の法人の証明書の原本の提示
非対面での契約
・登記事項証明書等の法人の証明書の原本又は写しの送付+本店等の所在地に携帯電話端末や契約関係書類を転送不要郵便物等で送付
・電子署名及び電子証明書を付した本人特定事項の送信
※契約者が法人の場合、実際に会社の代表者や契約担当者の本人確認も必要です。
本人確認方法は契約者が個人の場合と同じ方法となります。
本人確認書類とは
契約者が個人の場合
(1)対面で提示することで本人確認を完了できる証明書
(契約者本人の氏名、住居、生年月日の記載があるものに限る)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書
被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険)
健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合証、地方公務員共済組合証、私立学校教職員共済制度加入者証、自衛官診療証
国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
以上のほか、官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、契約者の氏名、住居及び生年月日に記載と契約者の顔写真があり、一つだけ発行・発給されているもの
※日本に住居のない外国人の場合、上記の本人確認書類の他に、外国政府や国際機関が発行した書類で、上記の本人確認書類に準じた書類も利用可
(2)オンラインで、ソフトウェア等を通じて送信できる証明書
マイナンバーカードや運転免許証等の契約者本人の顔写真があり、本人特定事項が記載されたICチップが付属している公的証明書(写真付き本人確認書類)
(3)提示や送付を受けることに加えて、携帯電話端末などの送付が必要な証明書
印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票
官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので(ア)契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があるが、契約者の顔写真がないもの、又は(イ)顔写真があっても複数発行・発給されたもの(例えば各都道府県の発行している介護保険や児童福祉手当における需給資格証明書など)
非対面契約で送付される(1)の①~⑤の書類の写し
2.契約者が法人の場合
(1)登記事項証明書、印鑑登録証明書
(2)官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、法人の名称及び本店等の所在地の記載があるもの
本人確認後に対応が必要なこと 「本人確認記録」の保存
携帯電話事業者は、契約時の本人確認を行った後、速やかに本人確認に関する事項などを「本人確認記録」として記録を作成する必要があります。
そしてこの「本人確認記録」は、携帯電話の契約期間中はもちろん、契約が終了した後も3年間保存しなければいけません。
なお、「本人確認記録」に記載すべき事項は次のとおりです。
事業者側に関係する事項
- 本人確認をおこなったものの氏名(又は その者を特定するに足りる事項)
- 本人確認記録の作成者の氏名(又は その者を特定するに足りる事項)
契約者側に関係する事項
- 本人確認を行った日付
- 本人特定事項
- 本人確認を行った方法
- 本人確認に用いた書類・電子証明書の種類+記号番号その他の当該書類・電子証明書を特定するに足りる事項※
※マイナンバーや基礎年金番号等、法令により控えることやコピーを取るについては制約がある番号については、その番号事態を記録するのではなく、他の情報(発行元機関名や別の識別記号等)を記録するよう注意が必要です。
契約者の確認とは
警察から携帯電話が犯罪利用されている等の通知を受けた場合、携帯電話事業者は契約者の確認を行うことができます。
携帯電話が、携帯電話不正利用防止法に違反して譲渡等されている場合や、詐欺や恐喝等の犯罪に利用されていると認められる場合に、警察署長の求めに応じて携帯電話事業者が当該携帯電話の契約者について本人確認を行い、確認ができない場合はサービスの停止などの措置をとることができます。
違反行為とは また違反行為の罰則とは
携帯電話事業者や代理店の違反行為
①携帯電話契約時及び譲渡時に本人確認を行わない
②「本人確認記録」を適切に作成しない、契約終了から3年間保存しない
→上記義務に違反したとき、総理大臣は是正命令を発することができます。
命令に違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
契約者の違反行為
①携帯電話の契約時に氏名、住居及び生年月日について虚偽の申告をする
→本人特定事項を隠蔽する目的で行う場合、50万円以下の罰金に処せられます。
②事故の名義の携帯電話を、携帯電話事業者に無断で他人に譲渡する
→携帯電話事業者の承諾を得ずに、業として、有償で譲渡すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金に処せられます。
③他人名義の携帯電話を譲渡したり、譲り受けたりする
→50万円以下の罰金に処せられます。
勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金に処せられます。
今後、携帯電話契約時のオンライン本人確認手法は公的個人認証サービス(JPKI)への一本化の方針
近年、SNSやキャッシュレス決済の普及が進む中で、巧妙化・多様化したSNS型投資詐欺やロマンス詐欺等による被害が急増している状況をうけて、政府より「国民を詐欺から守るための総合対策」が2024年6月に取りまとめられました。
その中で「犯罪者のツールを奪う」ための対策の一つとして、今後携帯電話や電話転送サービスの契約時のオンライン(非対面)での本人確認手法はマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)に原則一本化する方針が示されています。
運転免許証を送信する方法や顔写真のない本人確認書類は廃止する方向です。
また、対面の契約時においてもマイナンバーカード等のICチップ情報の読取などを義務付け、ゆくゆくは公的個人認証サービス(JPKI)による本人確認を進める方針です。