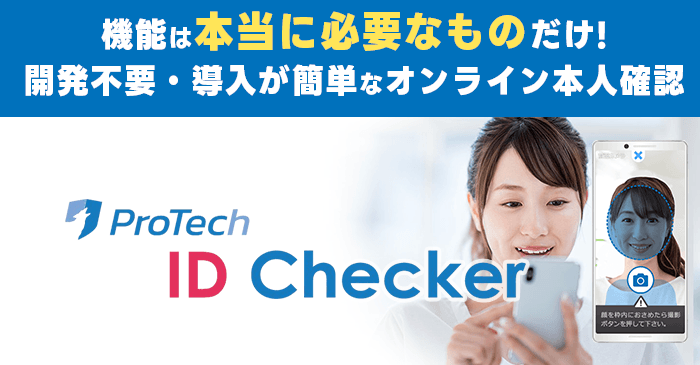婚活・マッチングアプリの本人確認|事業者に必要な出会い系サイト規制法を解説
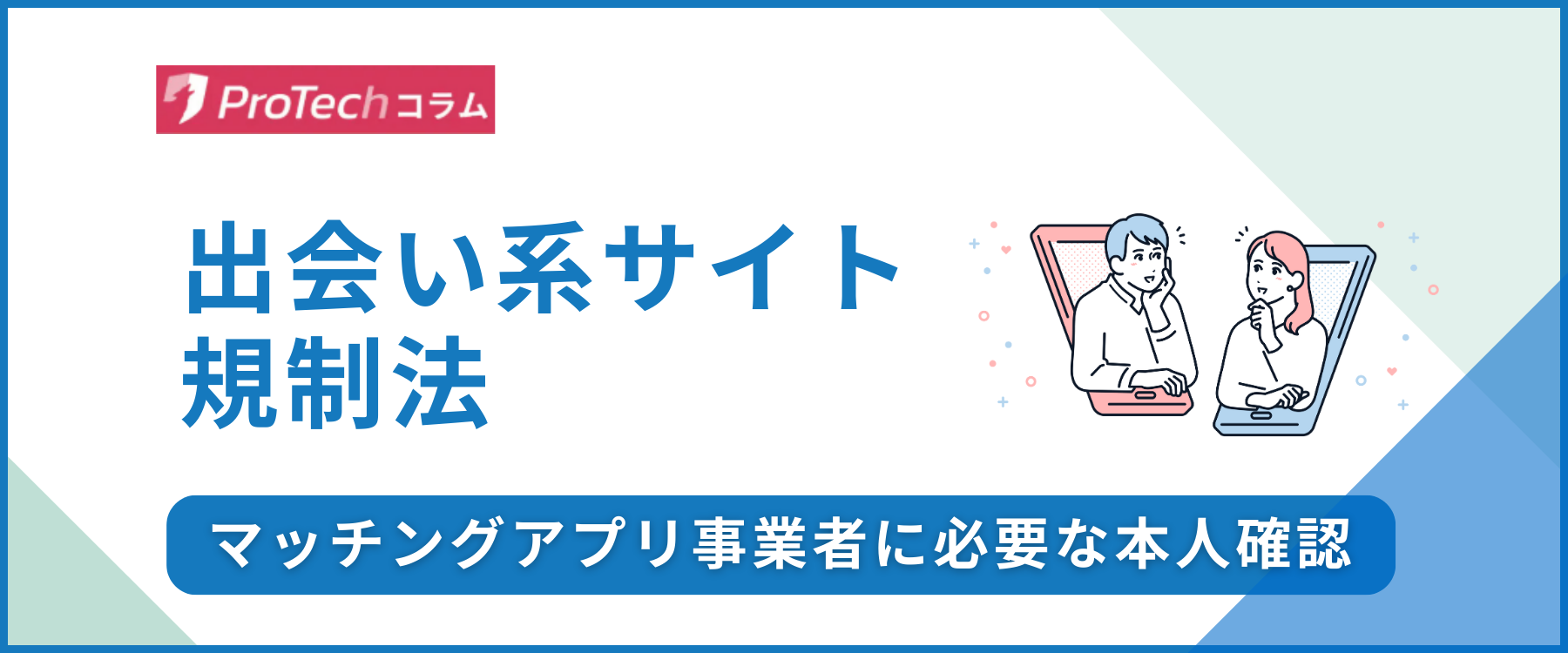
これらのサービスは、男女の出会いの選択肢を広げられるというメリットがある一方で、いわゆる「ロマンス詐欺」や、児童が犯罪に巻き込まれるといったリスクも高まっています。そのため、この分野でサービスを提供する事業者には、「出会い系サイト規制法」に基づき、厳格な年齢確認などの対策が求められています。
本記事では、マッチングアプリや婚活サイト等を運営している事業者向けに、「出会い系サイト規制法」の概要や届出義務、禁止事項などについて詳しく解説します。
引用元:警視庁「出会い系サイト規制」
出会い系サイト規制法とは?制定の背景とその後の改正の流れ
出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は、犯罪から児童を保護し健全な育成に資することを目的として、2003年(平成15年)に制定されました。しかし、制定後も依然として出会い系サイトの利用と起因とした犯罪が相次いだことから、2008年(平成20年)に事業者に対する規制強化を中心とした法改正が行われました。
さらに、2019年(令和元年)には、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の制定により、出会い系サイト規制法の欠格事由に係る規定も見直され、同年12月14日から改正内容が施行されています。
犯罪から児童を保護し、健全な育成を図ることが目的
「出会い系サイト規制法」は、児童買春や誘拐などの犯罪から18歳未満の児童を守ることを目的に制定されました。この法律は、出会い系サイトを運営する事業者に対して厳格な規制と義務を課すことで、児童の健全な育成と安全なインターネット環境の整備を図るものです。なお、この法律における「児童」とは、18歳未満のすべての少年少女を指します。
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の定義
出会い系サイト事業者を「インターネット異性紹介事業」と呼び、以下の4点を全て満たす事業と定義されています。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
インターネットを通じて結婚相手を紹介する婚活サイトはもちろん、スマホアプリから24時間いつでもお相手探しができる婚活・恋活マッチングアプリも、「インターネット異性紹介事業」に該当し、規制の対象となります。
また、法人だけでなく個人が提供するサービスであっても規制の対象となります。提供者の形態にかかわらず、適切な届け出や法令遵守が求められる点に注意が必要です。
インターネット異性紹介事業の届出義務

インターネット異性紹介事業を始めようとする場合は、事業開始前日までに事務所の所在地を管轄する都道府県交換委員会に対し、諸葛警察署長を経由して届出を行う必要があります。この届出には、国家公安委員会規則で定められた必要書類を添付をすることが義務付けられています。
また、事業を廃止した場合や届出内容に変更が生じた際は、廃止・変更の日から14日以内にその旨の届出をしなければなりません。添付書類の詳細は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則において定められています。
参考:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索
インターネット異性紹介事業の欠格事由
以下の1~7のいずれかに該当する場合、インターネット異性紹介事業を行うことが法律で禁止されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第百八十二条、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
- 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までに掲げる者か児童に該当する者
注意点として、インターネット異性紹介事業者は「名義貸し」も禁じられています。事業者は、自己の名義をもって他人に出会い系サイトの運営を行わせてはいけません。
インターネット異性紹介事業者の義務
インターネット異性紹介事業者は、18歳未満の児童による出会い系サイトの利用防止に努める責務が定められているほか、事業を行うにあたり以下のようなことが義務付けられています。
1.児童による利用禁止の明示(広告又は宣伝をするとき)
事業者が広告又は宣伝を行う場合、「18歳未満は利用できません」など、児童が利用してはならない旨を分かりやすく表示しなければなりません。
2.児童による利用禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)
事業者は、ユーザーが「児童でないことの確認」を受ける際、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨をウェブサイト上に表示するなどして利用者に伝達することが義務付けられています。
3.児童でないことの確認
事業者は、ユーザーがサービスを利用する際に、児童(18歳未満)でないことを確認することが義務付けられています。
原則として、利用の都度①または②の方法をとるか、①または②の確認を受けた者にID・パスワードを付与し、利用の際には当該識別符号の送信を受けることが義務付けられています。
①ユーザの運転免許証、国民健康保険被保険者証その他年齢又は生年月日を証する書面のうち
- 年齢又は生年月日
- 書面の名称
- 書面の発行・発給者の名称
に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送付を受けること
②クレジットカードでの支払い等児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること
4.公衆閲覧防止措置
事業者はサービス運営中に「禁止誘引行為」(児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み)を確認した場合、速やかにその内容を削除し、他の利用者がその情報を閲覧できないようにする措置を講じる義務があります。
年齢確認にとどまらず、本人確認まで行う流れが拡大中

婚活・マッチングアプリなどのインターネット異性紹介事業者が求められる法的な要件は「年齢確認」のみですが、自社サービスの安全性や信頼性を保証するために「本人確認」を実施する事業者は増えています。
なお、年齢確認と本人確認は混同されやすいものですが、実際には明確な違いがあります。年齢確認のために身分証のコピーや画像を取得しても、それだけで本人確認が完了するわけではありません。
■年齢確認
提出された書面の年齢、または生年月日、書面の名称、書面の発行・発給者の名称の3点を確認し、18歳以上であることを確認します。
■本人確認
マッチングアプリなどのサービス利用者が実在する人物であることを公的な書類等で確認する「身元確認」と、提出された本人確認書類の人物とサービス利用者が同一人物であることを確認する「当人認証」の両面から本人確認を行います。
本人確認の場合、年齢確認に加えて身分証明書の厚みの確認や、ライブネスチェック(カメラの目の前に本人がいることを判別する)などがあるため、年齢確認よりもなりすましが難しくなり、より安全性は高くなります。
本人確認は年齢確認よりも厳格な手続きが求められます。適切に行うことでなりすましや不正利用の防止につながり、サービス全体の安全性と信頼性を高めることができます。
また、近年SNS型ロマンス詐欺の被害が全国的に急増している状況等を受け、政府より「国民を詐欺から守るための総合対策」が2024年6月に取りまとめられました。 SNS型ロマンス詐欺への対策の一環として、マッチングアプリ事業者には、公的個人認証サービスなどを活用した厳格な本人確認をアカウント開設時に実施することが義務づけられています。
本人確認を行うメリット
本人確認を行うことによるメリット・デメリットは以下のようなことが考えられます。
年齢確認は主に生年月日のチェックに留まりますが、本人確認ではこれに加えて、身分証明書の厚みや立体性の確認、さらにライブネスチェック(カメラの前に実際の本人が存在することを検証する技術)など、複数のセキュリティ要素が加わります。こうした仕組みにより、偽造身分証や他人の情報を使ったなりすましなど、不正利用のリスクを大幅に抑えることが可能になります。
悪質業者の登録や他人によるなりすましを防止することで、サービス全体の安全性と信頼性が向上します。これにより、ユーザーは安心してサービスを利用できる環境が整い、その結果として利用者の拡大にもつながる可能性があります。
とくにマッチングアプリや出会い系サイトなどのインターネット異性紹介事業では、メッセージのやり取りを経て実際に対面するケースが多いため、相手の身元が確実に確認されているかどうかは、サービスの健全性を保つうえで非常に重要なポイントとなります。
本人確認を行うデメリット
本人確認を行うことによるデメリットも確認しましょう。
本人確認書類の準備や手続きに、手間や時間がかかる場合があります。申込時の煩雑さから離脱につながる可能性があります。
年齢確認は送信された画像を確認するだけでも可能ですが、本人確認の場合は提出書類に記載された内容(住所・氏名・有効期限など)と、申込書類の内容が一致するかの確認が必要です。本人確認システムであるeKYCサービスの導入や運用には初期費用や月額利用料などのコストが発生します。
婚活・マッチングアプリの本人確認にはeKYCサービス「ProTech ID checker」がおすすめ
婚活サイトやマッチングアプリ、出会い系サイトなど、オンライン型の出会いを支援するサービスは年々増えています。その背景として「安全性の向上」が挙げられます。
事業者は、18歳未満が利用できないような年齢確認の義務はもちろん、個人情報の保護や通報システムの充実など、ユーザーが安心して利用できる環境づくりに努めています。そんな中、サービスの安全性や信頼性の向上を目的に、オンライン本人確認サービス(eKYC)を導入する事業者は増えています。
ショーケースが提供するオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設、携帯電話の契約、古物品の買取、マッチングサービスのアカウント登録時などにおいて、本人確認をオンライン上で完結できるSaaS型のサービスです。マイナンバーカードのICチップを用いた公的個人認証(JPKI方式)や、顔撮影(セルフィー認証)と本人確認書類の照合に対応しており、スマートフォンやWEBからスムーズに本人確認手続きが行えます。
インターネット異性紹介事業におけるオンライン本人確認サービス(eKYC)はもちろん、そのほかのサービスにおいても本人確認業務のオンライン化についてお困りの際は、当社までお気軽にお問い合わせください。